掲載記事
新文化 2010年02月18日号 (2010/02/18)
コラム「風信」:著者のロングテール化が生むモノ
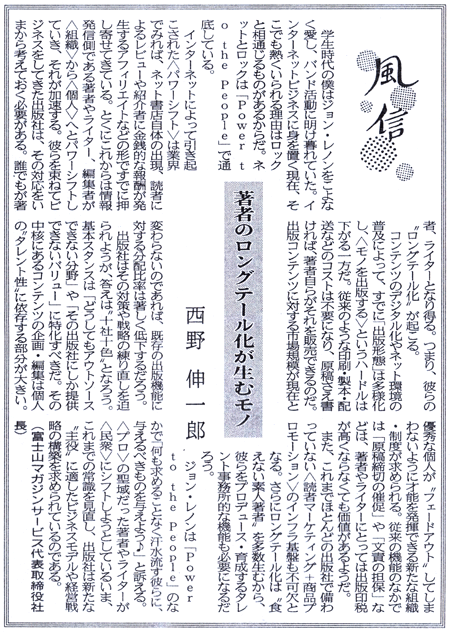
学生時代の僕はジョン・レノンをこよなく愛し、バンド活動に明け暮れていた。インターネットビジネ スに身を置く現在、そこでも熱くいられる理由はロックと相通じるものがあるからだ。ネットとロックは「Power to the People」で通底している。
インターネットによって引き起こされた〈パワーシフト〉は業界でみれば、ネット書店自体の出現、読者によるレビューや紹 介者に金銭的な報酬が発生するアフィリエイトなどの形ですでに押し寄せてきている。とくにこれからは情報発信側である著者やライター、編集者が〈組織〉か ら〈個人〉へとパワーシフトしていき、それが加速する。彼らを束ねてビジネスをしてきた出版社は、その対応をいまから考えておく必要がある。誰でもが著 者、ライターとなり得る。つまり、彼らの〝ロングテール化〟が起こる。
コンテンツのデジタル化やネット環境の普及によって、すでに「出版形態」は多様化し、〈モノを出版する〉というハードル は下がる一方だ。従来のような印刷・製本・配送などのコストは不要になり、原稿さえ書ければ、著者自らがそれを販売できるのだ。出版コンテンツに対する市場規模が現在と変わらないのであれば、既存の出版機能に対する分配比率は著しく低下するだろう。
出版社はその対策や戦略の練り直しを迫られようが、答えは十社十色となろう。基本スタンスは「どうしてもアウト ソースできない分野」や「その出版社にしか提供できないバリュー」に特化すべきだ。その中核にあるコンテンツの企画・編集は個人の〝タレント性〟に依存す る部分が大きい。優秀な個人が〝フェードアウト〟してしまわないように才能を発揮できる新たな組織・制度が求められる。従来の機能のなかでは「原稿締切の 催促」や「文責の担保」などは、著者やライターにとっては出版印税が高くならなくても価値があるようだ。
また、これまでほとんどの出版社で備わっていない〈読者マーケティング+商品プロモーション〉のインフラ基盤も不可欠と なる。さらにロングテール化は〝食えない素人著者〟を多数生むから、彼らをプロデュース・育成するタレント事務所的な機能も必要になるだろう。
ジョン・レノンは「Power to the People」のなかで「何も求めること なく汗水流す彼らに、与えるべきものを与えよう♪」と訴える。〈プロ〉の聖域だった著者やライターが〈民衆〉にシフトしようとしているいま、これまでの常 識を見直し、出版社は新たな〝主役〟に適したビジネスモデルや経営戦略の構築を求められているのである。

